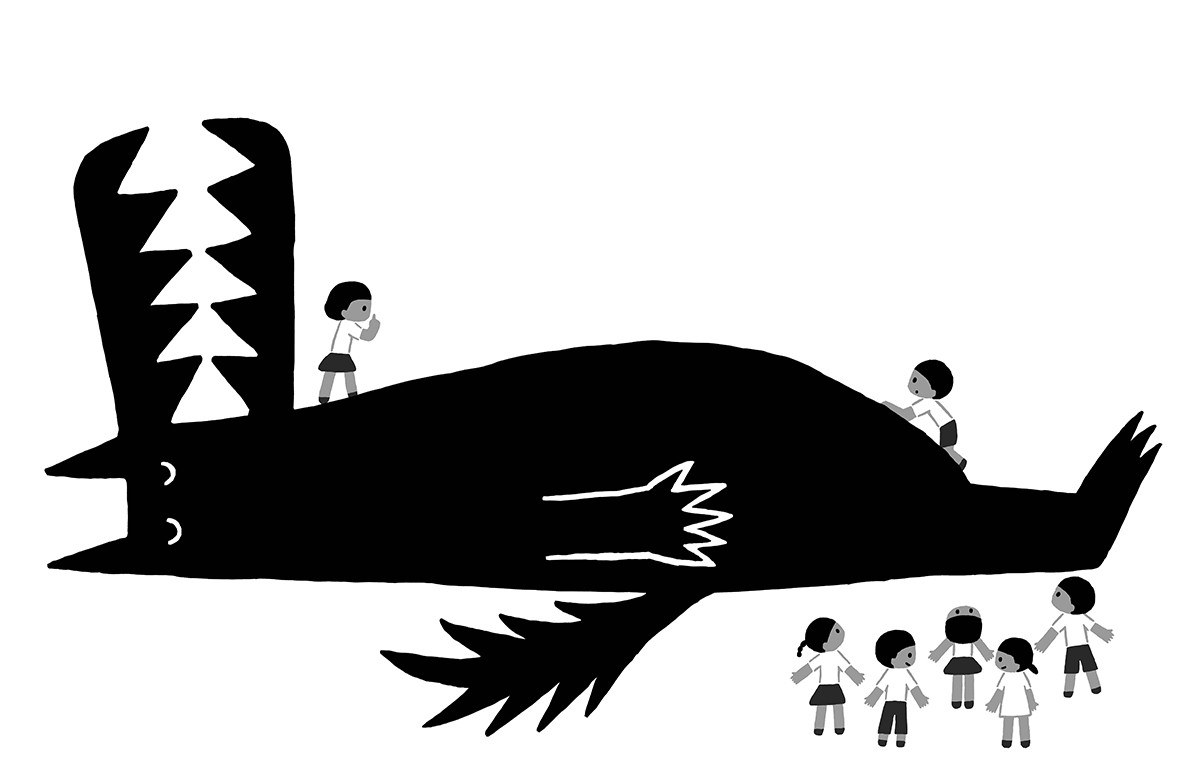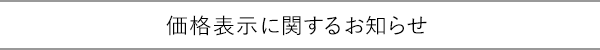映画『真実』。“母”に憧れた大女優の生き様から読み解く、親子関係の在り方

無条件で親は子を愛し、子は親を愛している。しかし、その愛が複雑な場合もあり、「愛している」「大好きだよ」と素直に伝えられなかったり、本音を隠したまま何年も過ごしてしまう人もいる。映画『真実』では、女優とその娘の、長年に渡る確執をゆるやかにほぐしていく物語を描いている。親子は、一番近くにいながら距離感が難しいもの、そして三者三様の在り方があると感じられる作品だ。
物語の舞台はフランス、主人公のファビエンヌは、国民的大女優で間もなく自伝本が発売される。出版祝いのために、ファビエンヌの娘リュミールと夫ハンク、娘のシャルロットがニューヨークからやって来る。リュミールは海外で脚本家として活躍するが、かつては母と同じ女優を目指していた。
事前に原稿を見せる約束だったが、チェックできないまま出版されたことに憤りを隠せないリュミール。そして、届いたばかりの自伝本『真実』を読んで、「この本のどこに“真実”があるのよ!」と母に詰め寄る。本には、事実と異なることが書かれていたのだった。

ファビエンヌは、「事実は退屈よ」と言い放つ。しかし、リュミールが「サラおばさんの名前が出てこないのはなぜ?」と言った途端、不機嫌になる。サラは、ファビエンヌの女優仲間であり親友で、リュミールが幼い頃から慕い懐いていたが、若くして亡くなってしまったのだ。
サラが亡くなって以来、ファビエンヌはずっとサラを意識していた。次に出演する映画も、“サラの再来”と言われる新鋭女優が出ているから出演を決めたとまわりは言う。映画の撮影が始まる中、リュミールは自伝本に書かれなかった、様々なエピソードを思い出し始める。ファビエンヌもリュミールが突きつける事実に、思いを少しずつ明かしていくのだった。
ファビエンヌは、「女優として優れていれば、ひどい母で妻で友人でも構わない」と豪語する。プロの仕事人だったが、実のところ“母”に一番憧れていたように感じる。娘から一番に愛され頼りにされ、自分もそれに応えたいと思っていた。しかし、女優であることのプロ意識やプライド、娘が親友になついてしまったことで気持ちを隠して生きてきてしまった。

そんな中、ライバルだった親友に似た新鋭女優と共演し、自分が子ども役を演じることによって、初めて子の気持ちが分かり、本心に気づく。「誰よりも娘を愛していたし、大切にしていた」と。
娘リュミールは「母から愛されていなかった」と思い込み、距離を置き続けていた。ファビエンヌは大女優として生きることを一番に考え続けた。結果、長年交わることがなかった2人が密になって向かい合うことになる。それによって、互いが感じていた愛情不足を確かめ合うのだ。
親子には、常に「話し合う場所」「向き合う時間」が必要だ。しかし、そこに“真実”“本音”はいるのだろうか。個人的には、知らなくてもいいこともあるような気がする。血の繋がった相手だからこそ大事にしたい「建前」や「礼儀」のようなものが、よりちょうどいい関係性にしてくれるのではないか。言葉で本音を確認しなくとも、ニュアンスや空気感から感じ取れることが真実のようにも感じる。

親は決して完璧ではない1人の人間だ。女優としては一流でも、母親としては未熟なファビエンヌの姿には、ある意味勇気付けられる。「パーフェクトな母親でなくていい」「本音を語らなくとも、時間を共有することに意味がある」と思えれば、子育てもずっと楽になるだろう。
映画『真実』を観ると、自分の家族はどうだろうと考えてしまう。そして、家に帰ったら「話を聞いてみよう」「一緒に過ごす時間を増やしてみよう」と、在り方を考え直すきっかけになるはずだ。
![映画『真実』。“母”に憧れた大女優の生き様から読み解く、親子関係の在り方 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)
![映画『真実』。“母”に憧れた大女優の生き様から読み解く、親子関係の在り方 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)