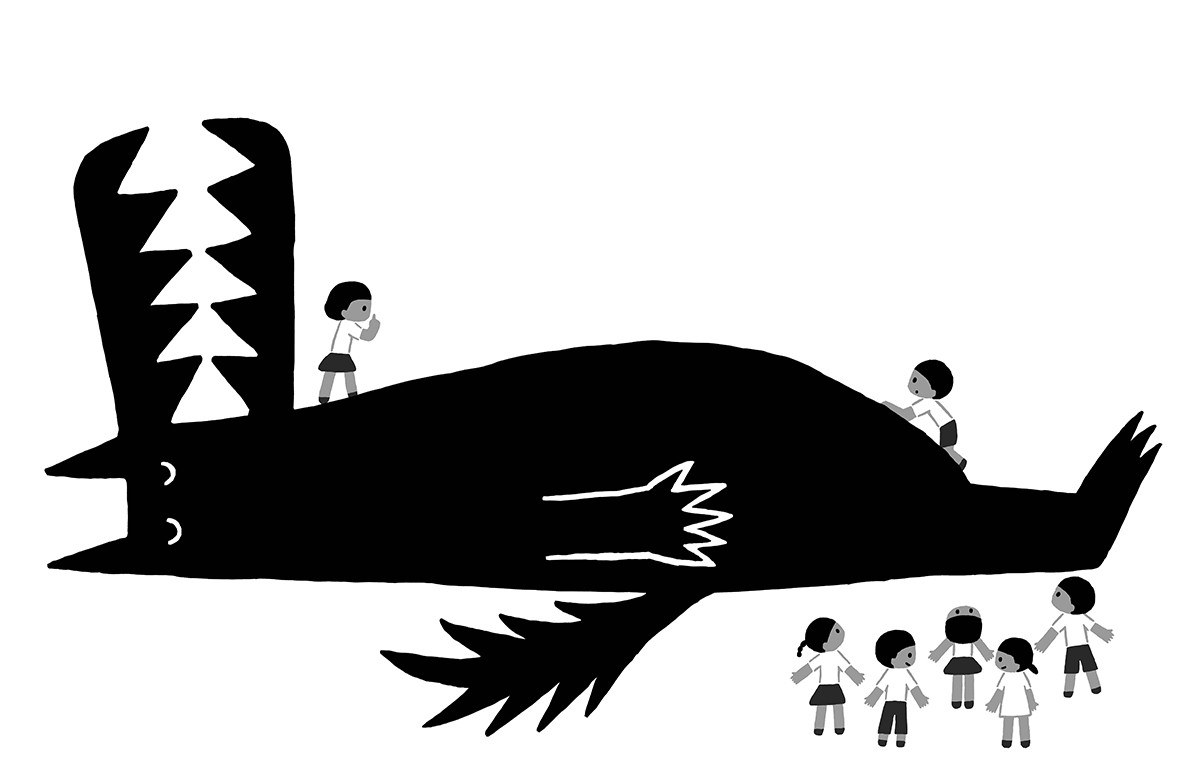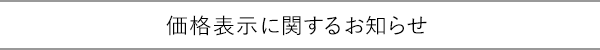しなやかに生き生きと。マイク・ミルズが描く魅力あふれる女性像『20センチュリー・ウーマン』
「まだまだこの世界に浸っていたい」。観終わった後も、そんな余韻に包まれる映画『20センチュリー・ウーマン』の魅力は、監督であるマイク・ミルズのあらゆるセンスが肌に合うこと、登場人物が嘘っぽくなく、とても魅力的であるところだと思う。

90年代のアート&カルチャーシーンを牽引するアーティスト、マイク・ミルズは、2005年に『サムサッカー』、2010年に『人生はビギナーズ』と2作の長編映画を手がけ、今作『20センチュリー・ウーマン』は3作目となる。
これまで青春時代や父親など、自身のパーソナルな部分に焦点を当てる作品を手がけてきたが、今回のテーマは母親。15歳の主人公ジェイミーを自身になぞらえ、思春期の息子に悩む母親ドロシアを自身の母親をモデルに生き生きと描いている。

舞台は1979年、アメリカの歴史的転換期。カリフォルニアのサンタバーバラで、シングルマザーでメーカーの製図師として働く55歳のドロシアは、息子ジェイミーについて悩んでいた。15歳で反抗期真っただ中、まったく息子の気持ちが分からないドロシアは、自宅の一室を間借りしている写真家アビーと、隣りに住むジェイミーの2歳年上の幼なじみジュリーに相談をする。「今の時代に、自分を保つためにどう生きればいいか。ジェイミーに教えてあげて」と。
しかし、アビーとジュリーも、決してパーフェクトな人間でなかった。アビーは、アーティスト志望だが夢半ばにして子宮頸がんを患い、サンタバーバラへと戻ってきた。ジュリーは、セラピストの母を持つが、再婚した父、脳性麻痺の妹などに囲まれ家庭では満たされず、恋人を次から次に変え、セックスで心を埋めようとしていた。

ドロシアとジェイミーの親子、そこに寄り添う不器用な女性たち。一般的な教育論に収まらない2人の持論が、とにかくおもしろくて興味深い。例えばアビーは、落としたい女への接し方や会話の仕方を教えるし、ジュリーは、「セックスをすると友情が終わる」と信じ、ジェイミーとは絶対にセックスをしない。
そんな2人に導かれたジェイミーは、どんなふうに成長するのか? ドロシアとどんな親子関係にたどり着くのか? 最終的に、ドロシアはジェイミーのひと言に救われる。「他の誰でもなく、ママがそばにいてくれればいいんだ」。このメッセージは、子を持つ親全てに響く、最高の讃歌のようにも思える。

映画館でぜひチェックしたいのが、1979年当時を再現したインテリアやファッション。ドロシア役のアネット・ベニングが身につけていたブレスレットはミルズの母親の形見で、劇中で使用されているテーブルや椅子、ベッドフレームやランプも、実際にミルズが両親の実家から持ってきたものだそう。またジェイミーが着ていたTシャツも、ミルズが少年時代に着ていたものと同じロゴだそうで、ミルズ自身が暮らしていた当時の様子や雰囲気をありありと感じることができる。
冒頭に書いたように、登場人物が「嘘っぽくない」のは、ドロシアに加え、アビーもミルズの実姉がモデルになっているから。大人でありながらどこか少年のようでアンバランスな母ドロシア、アーティスティックで人生を模索するアビー、少女のようにはかなげだが大人びた一面をもつジュリー。人生のどこかで、一度は出会ったことがあるような身近な女性像に、誰もが親近感と魅力を感じるはずだ。

いつだって誰だって、ちょっとしたことにへこたれず、しなやかでタフに生きたい。子どもの反抗期も、夫婦の不仲も、恋愛の不調和も、さらりと乗り越えていきたい。1979年をたくましく生きる女性像でありながら、現代を生きる私たちにも不思議とフィットするのは、時代をとらえ続けるマイク・ミルズだからできたのかもしれない。『20センチュリー・ウーマン』の心地いい世界にただよう2時間。それだけで心身がほぐれて、しなやかに明日が迎えられそうな気がする。
![しなやかに生き生きと。マイク・ミルズが描く魅力あふれる女性像『20センチュリー・ウーマン』 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)
![しなやかに生き生きと。マイク・ミルズが描く魅力あふれる女性像『20センチュリー・ウーマン』 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)