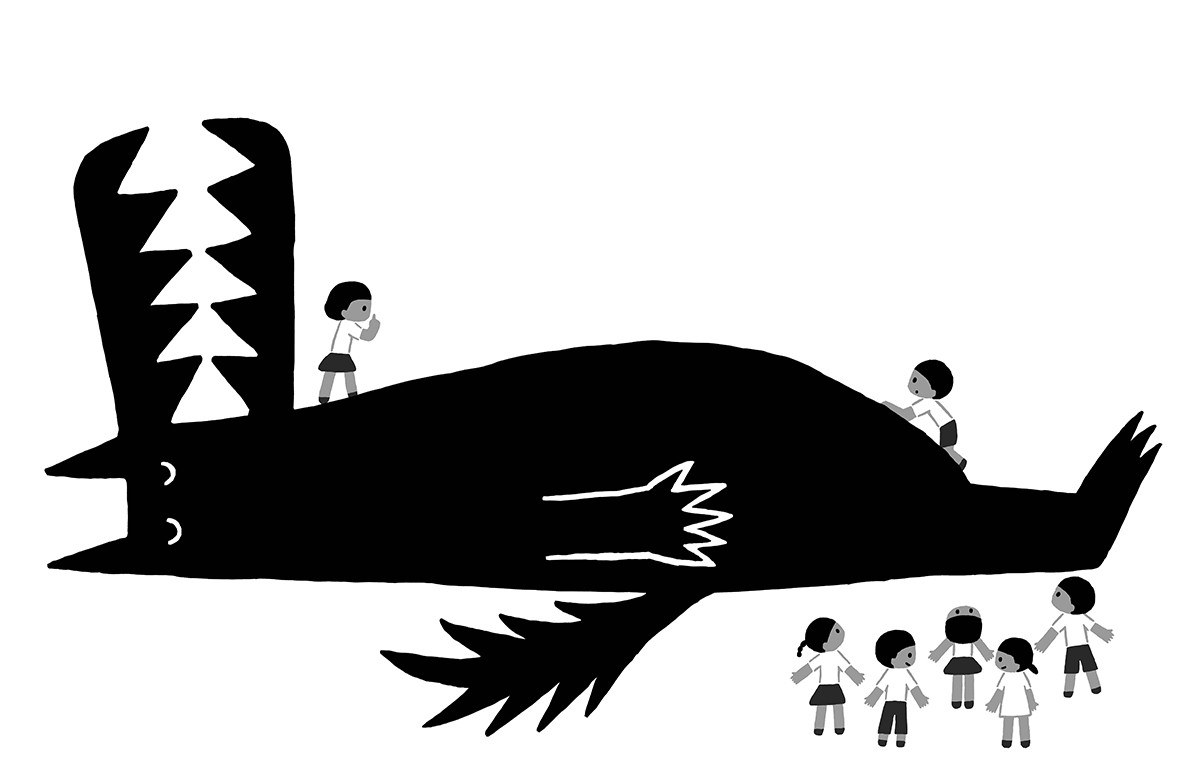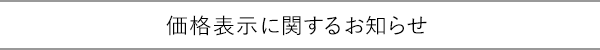10歳で将来の決断を迫られた少女時代。映画監督・安藤桃子に聞いた家族愛と高知愛

『0.5ミリ』などで知られる映画監督の安藤桃子さんが11月、初めての自叙伝『ぜんぶ 愛。』(集英社インターナショナル刊)を出版した。自身の子供の頃から、単身海外へ渡った時のこと、映画監督という仕事について、そして母になってから…。溢れるエネルギーとパッションを原動力に、自分の道を切り開いていくその生き方は清々しいまでに潔い。その中でも「ここまで書くの?」というほど赤裸々に綴られた家族や周囲の人々とのやりとりや、エピソードは、時に驚き、時に微笑ましく、そしてどれも温かく優しい。働く母としての思いや葛藤も丁寧に描かれ、Fasuファミリーの方々も共感を得たり、前向きになれるヒントをもらえるだろう。
そこで今回Fasuでは本書にまつわる話を安藤さんに聞いた。家族のこと、母として大人として今、子どもたちに対して思うことなど、そこにもやはりすべてに「愛」があった。

――今年4月にお嬢さんが小学1年生になられたんですね。新生活はいかがでしたか?
入学する前はかなりビクビクしてました。周囲の人たちから「小学校入ったら朝早いし、休めないし大変だよ」みたいな話を散々聞かされたんです。確かに幼稚園は親のリズムでいけるところがあるじゃないですか。仕事で連日徹夜続きで寝坊しちゃってチャリで送って10分遅刻してすみません、みたいなのが通用しないっていう。当たり前なんですけどね。
――小1の壁ですよね。どうやって乗り越えられましたか?
結構本気で「大丈夫だろうか!?」と。でもいざ学校が始まったら、私、切り替えが早いんですね。なのでやってみたら当日からバシッと変わりました。娘もそう。今になってみると、あそこまでの不安は必要だったのかな、と思ったり。「絶対に遅刻できない」という、暗示のような言葉に不安になっちゃって、ちょっと気持ちがワチャワチャしちゃったんです。それが娘にも伝わったはずで、入学前の「超楽しみ」なはずの気持ちを動揺させちゃったところがあって、それは反省点。
――小学校に入ると、そういった社会のルールのようなものを、実感することが増える気がします。
そうですね。でも、リモートでの仕事が普通になったじゃないですか。子供たちもコロナ禍があって時代が変化していくなかで学校行ってて、授業や行事のあり方も随分変わりましたよね。うちの娘が、小学校6年生になる時にはもしかしたら、朝この時間に行かなきゃいけないとか 、給食を揃って食べなきゃいけないとか、集団でみんな同じ方向を向いて座って勉強しなきゃいけないとか、「そうでなければいけない」っていうルールっていうものがなくなっているかも?ぐらいに思っています。子供は一人一人全く違うし、そこには正解なんてないですよね。

――娘さんはどんなお子さんですか?ご自身に似てるなって思うところはありますか?
エッセイにも書いたんですけど、私は本当にぼーっとしてる子だったんです。自分で進んで勉強をやったなんてことは一度もなかったし(笑)。それに対して娘は不思議なくらいちゃんとしてる。宿題も自分で先にやるし。ピアノを習っていて、私の都合でレッスンも休みがちだったりしたんですけど、最近になって突然思い立ったらしく、1回だけ「『猫ふんじゃった』教えて」って言うので教えたら、私がいない間に3日後には完璧になってたんです。誰に似たんだろう、っていう。そして女子力もある(笑)。洋服のコーディネートや髪型へのこだわりが強くて、この毛1本動かしちゃダメ、とか。私自身はめっちゃ憧れはあるのですが、女子力はたぶんかなり低いです。だってほんとエッセイに書いたとおり、朝、顔を見てお化粧したらそれきりって感じなんで。
――安藤さんは東京育ちですが、高知で暮らし、そこでの子育てはどうですか?
それがですね、いっぱい共通点があるんです。私が育った家の近所は麻布十番商店街があって、「麻布十番!?都会じゃん!」って思うかもしれないけど昔からある商店街なので、魚屋のおじちゃんとか豆腐屋のおばちゃんとか小さい時から顔馴染みなんです。初めてのブラジャーは商店街の洋品店とか。そういう地域のコミュニティの中で育った感じが、高知の今の家の周りと似てるとことろがあって。そこを歩けばみんな知ってて、見守ってくれている感じの安心感。
あと、うちは父親が毎晩映画関係の人たちを連れてきては、大勢で深夜、明け方まで飲んでる家だったんです。で、それが父の知り合いばかりじゃないという。知り合いが知り合いを連れてきて、またその知り合いも、みたいな感じで俳優さんもいれば付き人さんもいるし、本当にいろんな人が日替わりで来るんです。そんなのが普通の子供時代だったんですが、高知に来たらこれまたそういう家庭ばかりで。玄関がどこも空いていて勝手に入ってきて、人んちで飲み始める文化がある。どっちの宴会も、色んな人がいて、価値観が合わない者同士が同じ場所にいるのが当たり前。子供はそういうのを見ていろんな世界を学ぶんですよね。いろんな飲み方があるとか、飲まない人もいるんだとか、気を遣う人もいれば、そこでずっと寝てる人もいて、こういうことすると大人でも大人に怒られるんだとか。ああこういう態度はしたくないな、とか。こういう人は酔っ払いだけど優しいなあとか。
飲みの席に子供がいるなんて言うと、眉をしかめる人もいると思うんですけど、あの宴会でいろんなことを学べたし、高知で育っているうちの娘もそうだと思います。どっちもオープンな宴会というのが全く一緒。社会の縮図を垣間見る、みたいな。
コロナが流行してからは一切なくなりましたが、その辺の切り替えは高知の人たちは、めちゃくちゃ早かったです。

――家族だけじゃない大人を見る機会が安藤さんも娘さんもあったわけですね。その宴会エピソードをはじめ、著書で触れられているお父様であり俳優の奥田瑛二さんのエピソードはかなり強烈なものが多いですが、お孫さんであるお嬢さんに対してはいかがですか?
全然違う。びっくりします。エッセイにも書いたんですけど、私はプレゼントなんてもらったことないのに、孫にはプレゼントをあげてばっかり!「孫は娘の10倍かわいい」とか言っちゃって。「私の10倍かわいいってどういうこと?私がかわいいから10倍かわいいんでしょ?」って言ったら「いや、10倍かわいいのはシンプルに10倍かわいいんだよ」って。私もつい大人気なく噛みつきました(笑)。じいじが高知に来た時は娘と2人で自転車で海へ行ったりしていろんな話をしているみたいです。嬉しいですよね。
――お父様から「10歳までに自分の将来を決めなさい」と言われていた、とありましたが、娘さんにもそれは実行されるんですか?
全然考えてなかったなかったですね。私は私の人生の流れがあって、そういうタイミングが到来したけど、娘はまた違う人間で、違う人生だし、私と娘の関係も私と父とのそれとは全く違う関係だから、伝統を受け継ごうとはしなかった(笑)。じいじがするかもしれないけど、それはじいじと娘の間のことだから、それも娘の運命だよね。 そこに対してサポートはします!(笑)

――娘さんは安藤さんのお仕事をどんなふうに受け取っているようですか?
娘が2才のときにキネマMが開館して、よく連れて行ってたんです。夜遅い時間なんだけど上映が終わった後に、次の映画の試写をしたり、音や画面の調整するのを一緒に見ていました。うちはテレビをほとんど見なくて、映画をスクリーンで観るのが彼女にとっての原体験みたいな感じです。セルゲイ・ポルーニン(バレエダンサー)のドキュメンタリーがすごい好きで、3歳半ぐらいけどそれを観て映画館の外でダンスしたり。だからたぶん私がどんな仕事をしてるかっていうのはだいぶ早い時期からわかっていたんじゃないかなぁ。映画の撮影も一緒に来たりもしていましたし。友達や従姉妹たちと遊んでるのを見ていたら、ごっこ遊びのときとか「○○ちゃんはお母さん役でこんな感じね。△△ちゃんはこういうシチュエーションでこういう役ね、私はこういう感じ。はいじゃあとりあえずやってみよう!」とかめっちゃディレクションしてる(笑)。一人遊びの時も、ずっと会話してます、1人で。ただ、人前で踊ったり歌ったりというのはすごく嫌がります。それは私もそうだったからよくわかる。良くも悪くも自我に気づくのが早いんでしょうか。私がそうだったんです。人に見られるというのはどういうことなのか、自分てなんなのかを意識するのがすごく早かった。
――本を読んでいて感じたのは安藤さんのご両親ともに、子供を子供扱いしない、ということでした。それは安藤さんと娘さんの関係においても継承されている気がします。
私、子供に合わせて遊ぶことができないんです。だから遊ぶとなったら対等。本気しか出ない…(笑)。本気で外で遊んだり、工作するときも一緒にアイデア出し合ったり。親が子供に「教える」ってことでもないと思っていて。なにより子供たちは「私たちの後」に生まれた人たち。つまり前の世代より進化した命であって、私たちのDNAの中にはない情報もちゃんと持っていたりするんだと思うので、子供だからわかんないっていうのは違うような気がする。子供は言葉ではうまく言えないから、キーってなるけど、言葉じゃない細胞レベルでは進化してる。私たちの未来の先輩なんですよね。次世代から教えてもらうことしかないって感じることが多いです。

――この時代、大人が教えることってどれくらいあるんだろう、とは思いますね。
はい。だからできることと言ったら、その子が好きなこと、一生懸命になれることを見つける環境を用意するってことかなあと。うちの母(安藤和津)は「どんな何の種かわからないでかぼちゃにバラの肥料一生懸命あげても、かぼちゃは育たないし、逆にバラの種子なのにカボチャの肥料をあげてもうまく育たない。それが何の種かって気付くためには色んな土壌を試してあげたらいい」と言ってたんです。そうやって試していくうちに「もしかしてこっちじゃないか」というものがあったら、大人が最初のうちは見てあげて、その子の“好き”な芽を育てられるようにしてあげられればと思っています。
――大人ができるのは結局見守ること、くらいなのかもしれないですね。
この子たちが幸せでありますように、と願う感じですね。そして子供ってやっぱりすごい。コロナが流行して、大人たちが不安になっていても子供たちは何も変わらない。マスクしててもお友達と仲良くなって、遊んで、笑って。その生命力っていうところにすごく大きなことを今気づかされます。不安の中にずっぽりはまって抜け出せなくなることが大人の場合はあるけど、そのループに子供を一緒に入れるべきではないなって思うんです。
生命と感性っていうのはどの子も変わらず、重い病を持って生まれてきたり、家庭環境が大変だったりしても、1人1人の子の命を見た時は全員もう涙が出るほど輝いて笑顔が美しいですよね。娘が幼稚園に通っているときPTA会長をやらせていただいたり、高知で「わっしょい!」(子供たちの未来を考える異業種チーム)でを運営していていろんな子供たちと出会う機会があるんですけど、本当にどの子も天才だと思う。全人類1人残らず持って生まれた資質を、まっすぐに伸ばすことができたら世界は大調和するだろうと思います。
――お子さんとの関係で一番大切にしていることはなんですか?
真心。ほんとにこれ。まことの心だから、優しくてあったかい、周りにもあったかくて優しくて、反対に優しくされてお互いに嬉しいみたいな。高知の人たちが本当にそれを教えてくれたと思います。自分だけ良ければいいっていうのが全然なくて、相手が喜んでくれたらもうそれだけでOK。
巡り巡って帰ってくるからって、みんな言ってます。何かしてあげたから帰ってくるんじゃなくて、そうやってみんなつながってるよって。
――高知での暮らしは安藤さんにとってとても大きなことなんですね。これからも高知で活動をされる予定ですか?
はい。ここからウェーブが確実に起こるような感覚があって。高知からいろんなことを起こしていきたいと思っています。

安藤桃子
1982 年、東京都生まれ。 高校時代よりイギリスに留学し、ロンドン大学芸術学部を卒業。 その後、ニューヨークで映画作りを学び、助監督を経て 2010 年『カケラ』で脚本・監督デビュー。2011年初の長編小説『0.5ミリ』を出版、2014 年監督・脚本し映画化。同作で第39回報知映画賞作品賞、第69回毎日映画コンクール脚本賞、第18回上海国際映画祭最優秀監督賞などその他多数の賞を受賞。2014年、高知県へ移住。ミニシアター「キネマM」の代表や、「表現集団・桃子塾」塾長、ラジオ番組「ひらけチャクラ!」(FM高知)のパーソナリティも務めている。また、子どもたちが笑顔未来を描く異業種チーム「わっしょい!」では、農・食・教育・芸術などの体験を通し、全ての命に優しい活動にも愛を注いでいる。
![10歳で将来の決断を迫られた少女時代。映画監督・安藤桃子に聞いた家族愛と高知愛 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)
![10歳で将来の決断を迫られた少女時代。映画監督・安藤桃子に聞いた家族愛と高知愛 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)