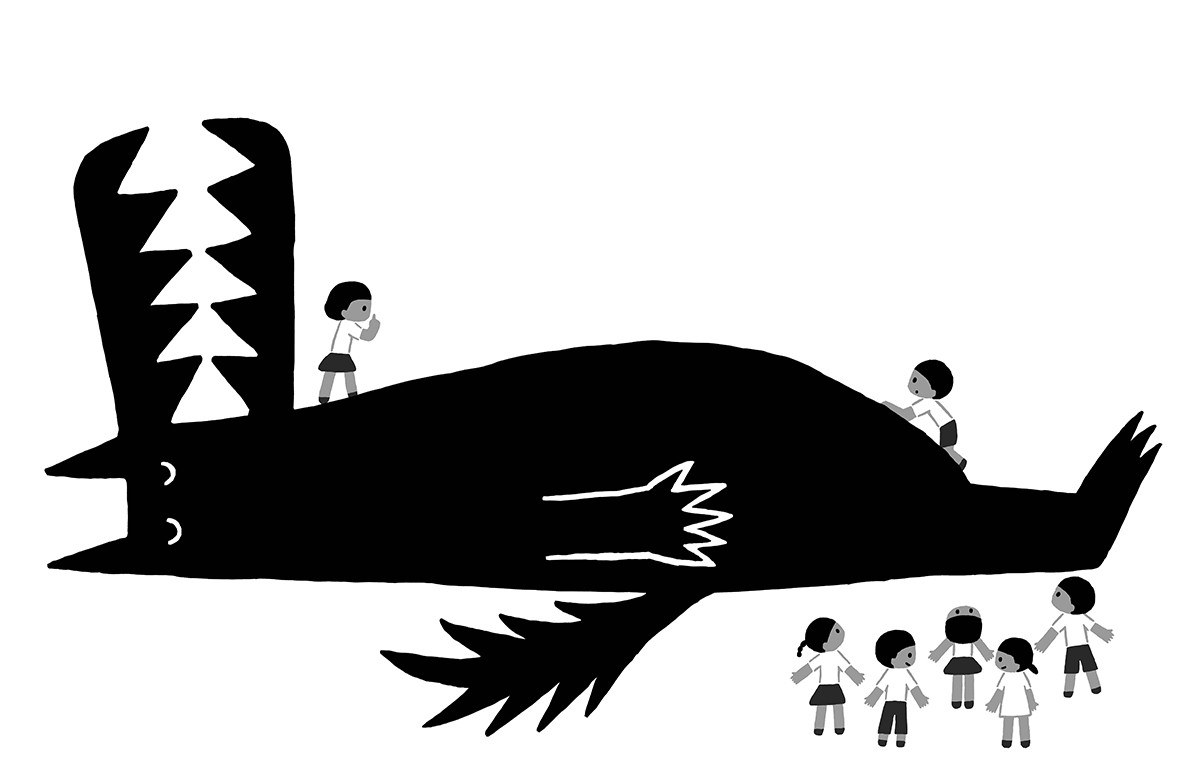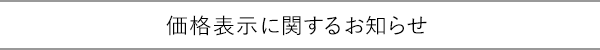「あの子のおやつ」その向こうに見えたことーイチゴイニシアチブのおはなし【前編】

現在、東京都内に存在する児童養護施設は約60箇所にも及ぶという。この日訪れたのは、都内23区内に位置する親による虐待や経済的理由など、諸事情により預けられた原則3歳から18歳までの子どもたちが集団生活をする、とある児童養護施設。こちらの施設では、幼稚園児から高校生まで様々な年齢の子5,6人により形成された「ホーム」と呼ばれる家族のようなグループに分かれて寝食を共にしている。最近はどの施設も大所帯より、そんな小家族形式を取ることが多いそうだ。
日頃は保育士や調理員、自立支援職員、心理士など専門的な役割を担う職員が、食事や日常、学習サポート、メンタルのケアなどを行う。学校の面談などは担当者が出席することもある。施設には18歳までしか住むことができず、この不安定なコロナ禍でも、頼れる実家がない子たちが、ギリギリで踏ん張っている。けれど、私たちが想像するような、どんより殺伐とした雰囲気は存在しない。まるで兄弟の多い、誰かの家にでも遊びに行ったかのような、からっと開けた空気がそこには漂っている。今どきのファッションや遊びを楽しむ彼女たちは、クラスの隣の席に座る女の子となんら変わりはない。

イチゴイニシアチブ、そのはじまりと実体
今日のできごとを語りながらおやつのクッキーを頬張る子どもたちの横で、まるで近所のお姉さんように相槌を打ちながら、温かい眼差しで見守るのは、「イチゴイニシアチブ」を主宰する市ヶ坪さゆりさんだ。穏やかな愛を360度から放ちながら、明るく、さりげなく児童やお母さんたちに寄り添う姿が印象的で、そんな姿にエネルギーをもらう人も多い。NPOのように組織化せずに身の丈に合った活動を行うことをベー
きっかけは2008年に起こった秋葉原通り魔事件。なぜこのような事件が起きたのか。
そのために、と市ヶ坪さんが最初に思い立ったのは、誰もが平等にひとつずつ持っている“お誕生日”を祝うこと。ただひたすら単純に、年に一度の特別な日を特別な衣装で存分に着飾った子どもたちに、「おめでとう」を届ける活動は、2010年に実現した。4月生まれの女の子4人に始まり、1年をかけてその施設で暮らす25人の女の子たち全員のお誕生日をお祝いすること。取り組む姿勢は丁寧に。
はじまりから終わり。そのすべてを全うしてほしい
七五三の当日はとにかくワイワイガヤガヤと賑やかに大勢のクルーで訪れ、子どもたちも施設スタッフも、全員がその祝い事を楽しむ。鏡の前の子どもたちは、特別な自分にドキドキとワクワクを隠せない様子だ。施設や学校で会う大人とは別の、大人たちとの生きた交流のなかで、子どもたちが、何かあたたかな幸せのイメージとともに様々な方向にアンテナを張るきっかけになれば。クルーは笑顔と全力で晴れの日を作り上げていく。ボランティアの活動だからと言って決して手を抜かないこと。それぞれの職業のプロがきちんと子どもに向き合うことで、彼らが未来に見える世界が変わってくると信じているから、と市ヶ坪さんは語る。
「イチゴイニシアチブ」というプロジェクト名には、始まりから終わりまでの一生を表す仏教用語の一期(イチゴ)の意味にも通じる。いまや訪れる施設は毎年約7ヶ所、七五三シーズンは特にてんてこ舞いだ。そんななか、何にも変えることができない喜びこそ、祝った子どもたちが、そのキラキラした記憶を大切にしてくれているという事実。施設を訪れるたびに、彼女たちは懐こく屈託のない笑顔で「七五三のお姉さんたち」である市ヶ坪さんらに愛らしくまとわりつく。この日おやつを食べていた子どもたちも、昨年の七五三で祝った女の子たちだ。

笑顔のなかに時折見せる不安な表情、楽しい会話に入り混じる、取りこぼしてはいけない悲しいエピソード。普段の交流や七五三を通じて知り合った一見ありふれた日常に暮らす子どもたちが、大人でも抱えきれないほどに、ずっしりと重いものを背負って生きている。福祉という枠にとらわれない活動を続けながら、彼女たちの人生の中に宝物をどんどん増やしていくこと。市ヶ坪さんが導く「イチゴイニシアチブ」は、ファッションや文化を介して、これからも子どもたちの素敵な記憶を紡いでいく。
![「あの子のおやつ」その向こうに見えたことーイチゴイニシアチブのおはなし【前編】 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)
![「あの子のおやつ」その向こうに見えたことーイチゴイニシアチブのおはなし【前編】 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)