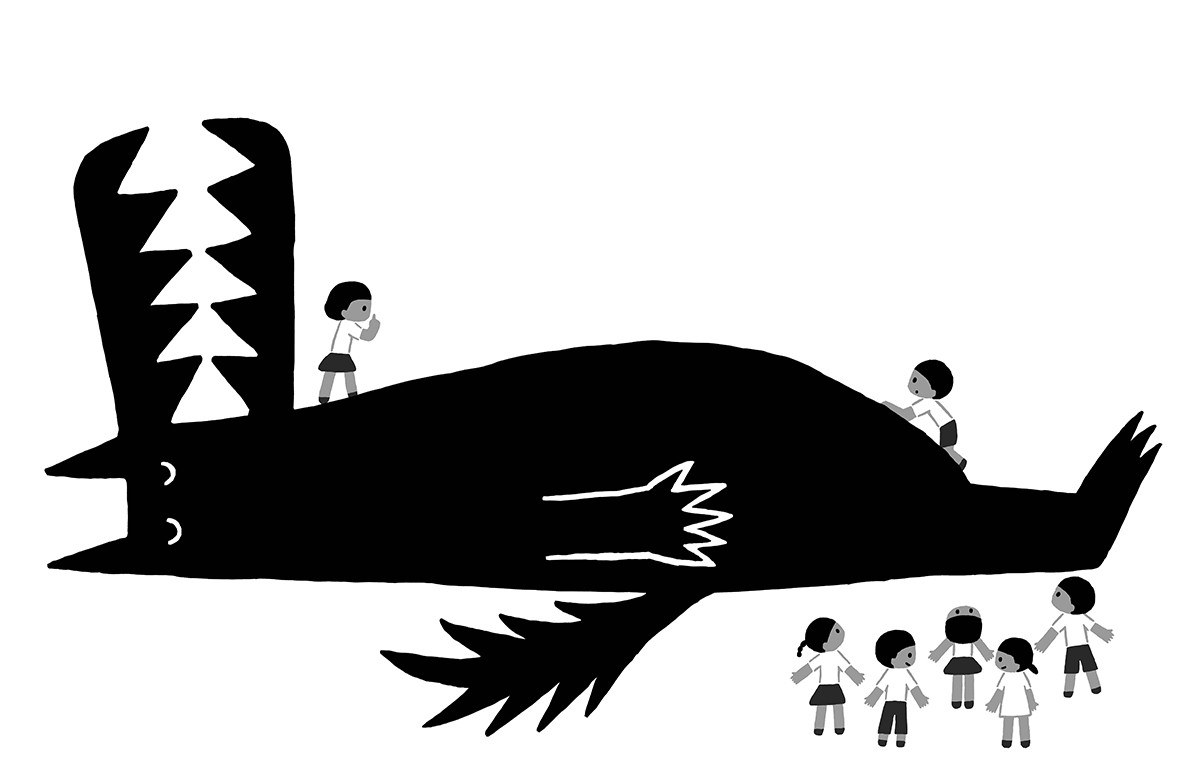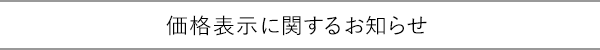グラフィックデザイナー長嶋りかこが明かす、本屋のない村で育った幼少時代の”少し変わった”絵本体験【絵本と本と私の物語 #04】
「札幌国際芸術祭2014」や「東北ユースオーケストラ」など、坂本龍一氏によるプロジェクトのデザインワークを数多く担当し、近年ではポーラ美術館のVI計画や、2021年度ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展・日本館のデザインを担当するなど、トップクリエイターとして第一線で活躍している、グラフィックデザイナーの長嶋りかこさん。
そんな日本のデザイン業界を牽引する彼女は、幼少期もクリエイテブなカルチャーの中で育ったに違いない、と思いきや、意外にも「子どもの頃は、自然しかない田舎で育った」という。そんな長嶋さんが、幼少時代の思い出とともに、小学生の頃に出会ったある絵本とのエピソードを語ってくれた。

言葉をうまく出せなかった、幼少時代
「実は私、親に絵本を読んでもらった記憶がないんですよね。家には本が少なく、両親は仕事で家にいないことが多かったので、恐らくそういう機会が無かったように思います。貧しい家だったので、物心ついた頃には親にねだって何かを買ってもらうことに罪悪感があって。本を買ってもらった記憶もほとんど無いんです。ただサンタクロースにねだった記憶はあり、3〜4才頃だった気がしますが、一番最初にお願いしたのは絵本ではなく『文字の練習帳』でした。絵を描くことが好きだったので、同じ感覚で文字も、書くというより“描く”という感じでその行為自体が好きでしたね」
人との交流が少なく、絵本や本との縁が薄い環境もあり、”言葉”が少ない子どもだったという長嶋さん。心の中で感触や匂い・感情・イメージは渦巻くものの、言葉の蓄積量の少なさから、それらをどう外に発すればいいのか手段が分からなかったと振り返る。
「小学校にあがり、国語の教科書ではじめて文章と対面したような感じでした。そこで詩というものにもはじめて触れ、自分も詩を書いてみたり。そこで感じたままに、想いを自由に放つことに居心地の良さを覚えたんです」
そんな彼女を変えてくれたのが、小学校一年生の時の担任の先生だ。その先生が絵や字、詩を褒めてくれたことで、長嶋さんの中で「表現」することへの意識が変わっていく。
「『草や花や虫とお話ができるピカピカのアンテナをもっているから、みんなにたくさん聞かせてね』と書いてくれたメッセージカードが残っていて、それは今でも宝物です。自分がどんな詩を書いていたかは、もう覚えていないんですけど(笑)。でも先生がそんな風に私を捉えてくれたおかげで、自分が描いたり作ったりするものはどんどん外に出していいんだと思えました」

私の地元には、本屋さんが無かった
生まれ育った地域は、信号機もバスも無い過疎地。山・川・田んぼ・畑が広がり、店がないので当然ながら本屋も無い。ではどのようにして、書籍に触れていたのだろう?
「確か何度か学校の計らいで、絵本を注文できる機会がありました。A4サイズに小さな文字でずらりと並んだ絵本のタイトルだけを見て、注文するんです。ジャケ買いならぬ『タイトル買い』ですね。さまざまあるタイトルの中で特にワクワク感が記憶に残ったのが、エリック・カールの『パパ、お月さまとって!』でした。夜の空に浮かぶ月を触ってみたい。どうやって月はあそこにいるんだろう。どうして光っているんだろう。どこまで行けば近づけるんだろう……。子どもがよくする想像を、例に漏れず私もしてましたから、このタイトルに想いを馳せマルをつけて注文しました」

絵本の魔術師と称されるエリック・カールが、娘のサースティンから「パパ、あのお月さまとって!」と頼まれた出来事をキッカケに誕生した本作。父親が娘のために空に浮かぶお月さまを取りに行く、という心温まるやり取りを通して、月の満ち欠けについても学べる作品だ。1986年の初版から、今もなお人気を博しているエリック・カールの代表作の一つであり、エリックらしさが光るダイナミックなイラストの世界観に、長嶋さんも夢中になった。
「初めてのエリック・カールの絵は、色合いも筆の走る勢いも造形も、今まで目にしたものとは違って、『ここではないどこかのものがきたぞ!』という感じでした。遠く(異国)からやってきた感じがまた、月という遠くのものを扱う絵本の世界にマッチしていて。でもその馴染みのなさに、戸惑った記憶もあります。本が大きく開いたり、どんどん上へ上へとページが伸びていく構造も初めてで。ストーリーに沿った仕掛けに、胸が踊りましたね」

親子の絆を結ぶ、「月」という存在
エリック・カールと娘のサースティンにとって、月が親子の絆を深めてくれる存在であったように、長嶋さんにも月にまつわる、ご両親との大切な思い出がある。
「かつて幼い私は月を見て『おつきさまにでんきがついた!』と言ったそうなんですが、子どもならではのその表現を、母は嬉々として宝物のように何度も話してくれました。一方父は、当時2歳くらいの私の歌声をカセットデッキで録音していて、『でーたーでーたーつーきーがー まあんままんまー』と歌う私の後ろで嬉しそうに話している声が残っていて。あれは私にとって、親の眼差しを感じることができる音ですね」

今回、何十年かぶりにこの絵本に触れた長嶋さん。幼き日の記憶に想いを馳せる横で、2歳の息子さんが嬉しそうにページをめくる。月をめぐる親子の絆は、これから長嶋さんと息子さんを繋いでいく。
「両親同様、私も息子が夜の空に浮かぶ月を見て『ちいさいたいよう』と言った時は、それだけで天才か!と親バカよろしく嬉しくなりましたね。そして月を見れば、覚えたてながら『でたでた つきがー まあるい まあるい まんまるいー』と私の幼少期よりも上手に歌う姿や、夜になると月を探して『どうやって月になるのかなー』と言う姿を見て、そろそろこの絵本を読み聞かせしてあげたいな、と思っているところです。親の眼差しはこうして連鎖するんですね」

![グラフィックデザイナー長嶋りかこが明かす、本屋のない村で育った幼少時代の”少し変わった”絵本体験【絵本と本と私の物語 #04】 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)
![グラフィックデザイナー長嶋りかこが明かす、本屋のない村で育った幼少時代の”少し変わった”絵本体験【絵本と本と私の物語 #04】 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)