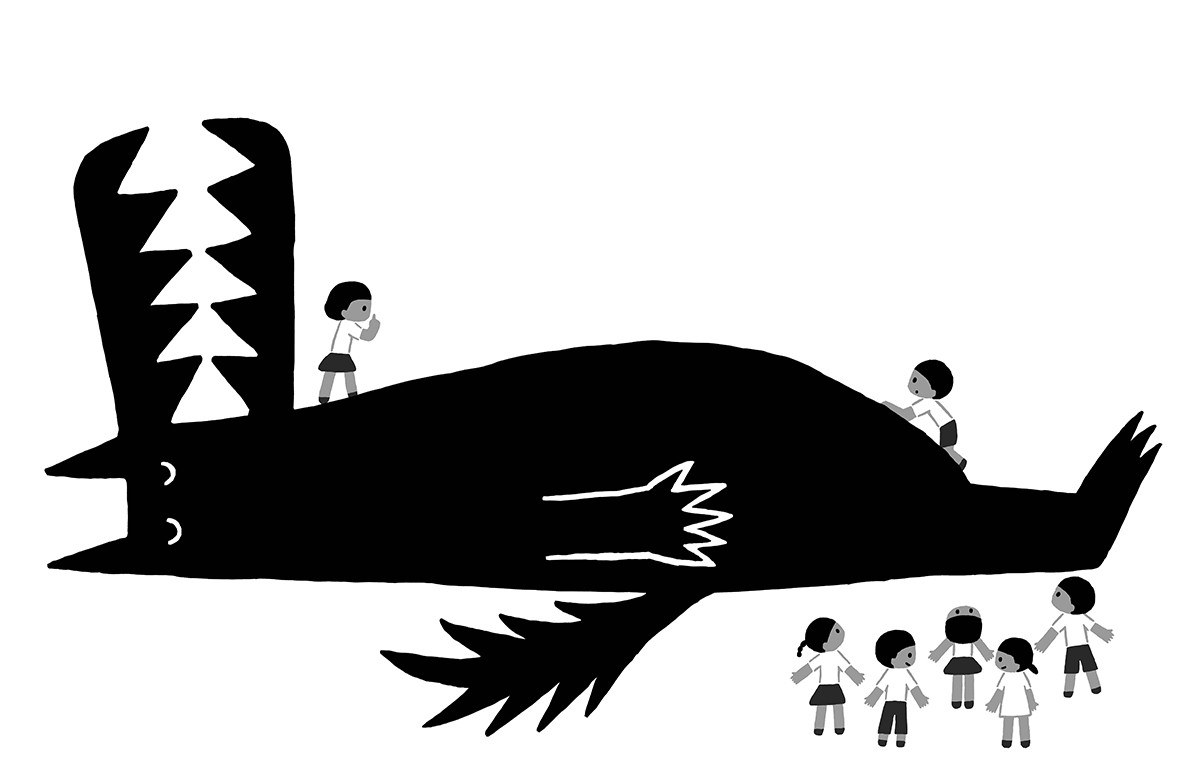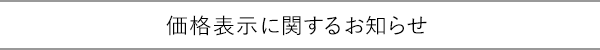体は「いちばん身近なおもちゃ」 ― 体が教えてくれること:第1回
その体、どんなふうに使ってる?
こんにちは、伊藤亜紗です。私は研究者で、人の体について研究しています。「人の体について研究している」というと、お医者さんとか、あるいは運動生理学といった分野のことをイメージされるかもしれません。だけど、私の研究はそういったものとはちょっと違っています。
この世にひとつとして同じ体はありませんよね。性別、身長、体重、顔つき、肌の色、運動能力、視力、聴力、声…みんな少しずつ、あるいは大きく違っています。そのひとつしかない体を、誰もが、その人なりの仕方で使いこなして生きている。医学や生理学は、人体を一般化・匿名化して扱います。〇〇さんの、〇〇さんならではの体、ではないのです。しかも、「治すこと」や「より良くすること」といった明確な目的を持って、体と関わります。

一方私の場合は、ひとりひとりの体の「違い」に目を向け、その人なりの使いこなし方を明らかにしたいと考えています。「治す」や「良くする」ではなく、その人がすでに行っている工夫や、習慣のようなものに注目します。最終的にはあらゆる体の違いが分かるようになったらいいな、と思っていますが、まずは体の違いが見えやすい人、具体的には障害のある人たちについて研究を進めてきました。例えば目の見えない人は、その視覚ぬきの体で、どんなふうに環境を認知しているのか。あるいは吃音があって言葉がスムーズに出ない人は、どんなふうに言葉と体の関係をとりもちながら、「しゃべる」という行為を遂行しているのか。
研究では、実際に当事者の方にインタビューをしながら、その人と一緒に、体との付き合い方を言葉にしていきます。「えっと、その体の使い方は…」。ふとしたエピソードに、驚きに満ちた発見が隠れていることもしばしば。健常者と呼ばれる人たちが、いかに体の限られた可能性しか使っていないか、日々実感します。
いちばん身近なおもちゃ
さて、こんなふうに私は、一つ一つの体の違いに注目しながら、その体ならではの使い方や、そのような体を抱えて生きるとはどのようなことなのか、を研究しています。でもこれって、研究者でなくても、誰もが普段から当たり前にやっていることなんですよね。例えば跳び箱が跳べないとします。跳ぼうとするとどうしても怖さが勝ってしまって、思い切り踏み切ることができない。どうやったら助走の勢いを消さずに跳び越すことができるんだろう……? 誰もがそんな、体の使い方をめぐる悩みに直面し、試行錯誤をした経験があると思います。
体が変われば悩みも変わるし、試行錯誤のポイントも変わります。目が見えなければ「まっすぐ歩く」ということがひとつのチャレンジになるし、下半身が動かなければ「腕の力だけで階段を下りる」ためにオリジナルの工夫が必要になる。年をとれば、食べ物を食べることだって冒険です。私の研究は、そんな誰もがやっている「体と付き合うための苦労や工夫」を、丁寧に言語化する作業だと言えます。言語化するのはなかなか容易ではありませんが、まあ、違いはそこだけ、と言うこともできます。

つまりは、生きていくというのは、つきつめれば自分の体との付き合い方を研究することなんじゃないか。人は、体を通して学び続ける。体は、誰にとってもいちばん身近な研究対象です。
あるいは、いちばん身近なおもちゃと言ってもいい。赤ちゃんが、いちばん最初に見つけるおもちゃは、まぎれもなく自分の体です。まだ生後2~3ヶ月のうちから、赤ちゃんはやたら自分の手を見つめ始めます。「ハンドリガード」と呼ばれる行動で、片手を見つめたり、両手を見つめたり、そのふたつを合わせてみたり。赤ちゃんは、どんなおもちゃよりも早く、まず「手」で遊んでいます。「 ハイハイ」や「たっち」をするようになれば、体をめぐる探究はいっそう高度になっていきます。ハイハイのスタイルひとつとったって、一様ではありません。定番の四つん這いスタイルの子もいれば、片ひざを立てて忍者のように進む子、両脚を投げ出してすべるように高速移動する子、本当にさまざまです。それはさながら、赤ちゃんひとりひとりの「どうやったらこの体を早く前に進められるか」の研究成果を見ているようです。
こんなふうに、体は、子どもにとっても大人にとっても最も身近な研究対象です。そうやって当たり前に研究していることを、言葉を使ってさらに深めていく。場合によっては、人とくらべてみる。そうすると、意外な発見に出合うことが多々あります。
本コラムのテーマは「あたらしい学びのかたち」です。体について考えることは、実はふるくてあたらしい学びの入り口なのではないかと思っています。
![体は「いちばん身近なおもちゃ」 ― 体が教えてくれること:第1回 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)
![体は「いちばん身近なおもちゃ」 ― 体が教えてくれること:第1回 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)